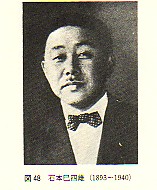東京帝国大学地震研究所 石本巳四雄
昭和四年二月七日の大阪朝日新聞 |
||||||
|
地震の本体が何物であるかは昔から大いに論ぜられたことで、現在においても一般の学者が信じてゐる定説があるとはいへない。これは地震学が学問として未だ極めで幼稚なものであって、将来の発達に十分の余地があることを物語るものである。
此の如き状態の下に大正十二年まで過ぎ來って遂に関東大地震が突発した。この時はかなりの地形変動すなわち相模、房州にわたって海岸の大隆起があつたが、大断層の出現は見つからなかった。この大断層の出現のないことを以て頗る意外とした人々は相模海底に大断層が成生されたものであるとの説を爲し、その地点から地震波動が四方に向って発散したと考へたのである。しかし、この海底断層の有無は全くの水掛け論で、相模湾の水を全部乾かしてしまはない限りは分からない。もっとも相模湾海底に何事も起こらなかったかというと、決してそうではなかった。
関東大地震に続いて大正十四年には但馬に地震が出現し災害を甚だしく蒙ったのは城崎、豊岡地方であつた。更に昭和二年には丹後に地震が見舞って但馬の震災以上の災害を齎したのである。 すなわち地震後直ちに三角及び水準測量が災害地にわたって数回繰返して施行せられ、地震後如何に土地が変動しつつあったかといふ事実が観測された。次に震源地より適当の距離に地震計三台(後に四台)が据付けられ、同時観測が行はれた結果、大地震後引続いて発生した余震の殆ど全部の位置が決定された。その他に傾斜計二台が宮津及び河辺村に据付けられ、地震後の地傾運動が余震に関係してどう変化したかが記録されたこと及び地形調査、地質調査が極めて精細に行はれたことも注意すべきである。 そしてこの研究の結果地震の本体に関するわれわれの態度も多く改易を必要とする機運に接したといひ得る。なかんずく水準測量によって得た結果からは注目すべきものが得られたのであって、地殻の構造は一辺約七粁の大さを有する地塊の集合から成立してゐること、しかも各地塊が数ケ月の間において測量し得べき傾斜運動をなしてゐる事実が明白となった。もちろん関東大地震の水準測量の結果からしても地塊構造の存在は十分認められたのであつたが、丹後地震後においてますます小地塊の存在とその運動とが確認されたのである。かような事実が明らかになって來ると、断層の正体も再び考へ直して見なければならなくなって來た。地震の烈しかった地方の地殻がすでに幾つかの地塊に分裂しているのであるから、断層の成生した箇所にのみ破壊があってそこから地震が起つたといふような考へ方は具合が悪くなってしまった。 事実は地震発生と同時に地殻が小地塊に分裂し、その各々が運動を開始し、その中に於いて最も相互運動の烈しかった場所に我々の目に触れる断層が出現したかの如く見られるのである。そしてここに地塊運動を発生する原因を考へなければならなくなって來た。 関東大地震に於いて前述の如く地変としては殆んど土地の隆起のみで大断層の出現はなかったがあれほどの災害を齎した地震動が発生されたのだ。これらの現象を綜合しで考へてみると、地形変動と地震波動発生の間には因果関係があるものではなくて、いずれも地下に存在する一原因から誘導されて一方には地形の変形を起し、他方には地震波動を発生する機巧を考へればよいのであって結局我々の知識経験に基づく判断に拠る外ないのである。 自分はこの問題の解決として地塊下に横たわる岩漿を考へ、その運動をもって地震出現の根源とするものである。これは塊形運動と地震波動発生とを説明する上に於いて巳むを得ず到達した結論に外かならない。地震が岩漿の存在に起因するといふ考へは、かって小川(琢治)博士によっても唱えられたものであるが、博士は專ら地質学的事実を根拠としておられたようである。 岩漿の研究は近年頗る進歩したものの一つであって、地中においてこれら物質の冷却し行く状態はかなり想像し得るものとなり、たとへそれは複雑なものであつても、地震を起すべき條件は、十分存在しているのである。すなわち冷却しつつある岩漿の蒸気圧はある温度において極大に達しするので、この作用により岩漿は外圧力に打勝ち、間隙を求めて貫入岩を成生するということがいひ得られる。この現象は要するに外力の蒸氣圧に抵抗する程度如何によって発生するものであるから外力と考へられるものの消長に大いに関係するといはなければならない。気圧の勾配が地震発生に影響する事実の中にはかようの現象が含まれているものと信ぜられる。かく地震現象は岩漿の運動により間隙が充填されることにより説明されるのであるが、この時の岩漿の運動速度には極めて大なるものがあって、間隙を充填尽くした時の運動量変化は甚.だ大であるといはなければならない。運動量変化は衝撃として地殻内に弾性波動を発生せしむる役割を演ずるものであり、この波動が地表に達する時に於いて我々は初めて地震の発生に気がつくのである。かように説明することによって地震波動発生の機巧は十分であると考へるが、大地震の場合に於いては、発せられた弾性波動の振幅が大であってこの歪みに堪へることのできない地殻は破壊を伴うことになる。震央附近において多くの地塊分裂が出現し、地塊全体として或は個々別々の運動が起こり、土地隆起或いは断層の成生が実現されるのはこの結果を物語るものであらう。すなわち断層の出現はむしろ地震後において極めて緩やかにズルズルとでき上って差支へないものである。 斯様に地震の根源に岩漿の作用を考へなければならぬ例証の一は傾斜計の観測によって地表傾斜の変化が地震発生前に甚だしく、地震と同時に静止することである。地震が断層成生によって発生するならば、地傾斜変化は地震の時或は地震後に烈しい筈であるのに全く逆であるのは岩漿の流動に依って地塊の傾動が起こり、流動の停止と同時に傾動も静止することを示すものと信ずる。又志田博士の唱へた深層地震の存在は和達理學士の四百粁の深さを持つ震源の存在で益々確実性を具へたが、此の深さでは地殻構造上の破壊は考へられないからやはり岩漿中に生じた変化を地震の原因と考へなければならぬ。 要するに地震の本体は岩漿の存在に原因する分化作用に源を発するものであつて、造山作用相まって岩漿の流動がひき起こされ、ここに地震が誘発されるものと信ずる。火山現象がいはゆる地震と無関係であるといふ事実から岩漿を云々することは地震の真相から遠ざかるものと見られていた時代もあつたが、今日においては岩漿の存在を度外視して地震を論ずることは不可能であるといっても過言ではあるまいと思う。本年一月二日阿蘇火山下に発生した強震は、火山活動と相待って岩漿流動の結果にほかならぬと信ずるものである。 地震の本源がすでに岩漿の存在によるものである上は、冷却に伴う岩漿の比重変化は地表にて観測する重力にも変化を及ぼす性質のものであつて、東京天文台における時計の遅速度変化も恐らくはこの間の消息を語るものではなかろうか。 終りに臨み一言附加するならば地震の本体が岩漿に起因するものと考へるからには、地震研究の一大綱目は岩漿研究を目的として進まなければならぬものであつて、地震国なる日本に於いて岩漿研究学者の続出とその奮起とを熱望してやまない次第である。 |
||||||