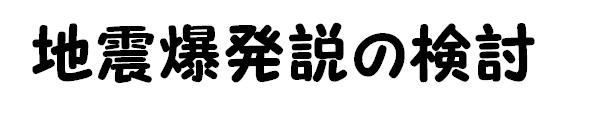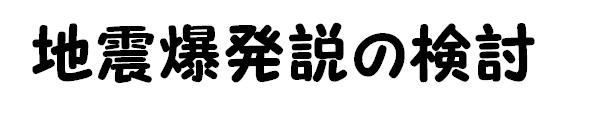| 誰でも分かる地球科学賖
テーマ:Earth Science
Wed, January 18, 2006 12:25:27
精神の回復を図るための第二回目。扱うテーマは・・・・「マントル」。
この領域は地球体積の大部分を占め、また地球の活動・進化に対
しても非常に重要な役割を担っているのに、一般的に大きな勘違い
が蔓延っていると思われる場所である。その「マントル」を今日は少し
詳しく見ていきたい。
マントル
「マントル」。マンホールにも響きが似たこの単語。意外に世間での認
知度は高い。巷間に溢れる「実際はあまりよく知らないけど名前は知っ
ているから、まぁ安心」といった単語の代表選手の一人だろう。この語
の次に認知度が高のは、「マントル対流」か?だがこの「対流」が誤解
勘違いを生む原因の一つなんだと思う。何の誤解か?そしてもう一つ
の原因は?気になるところだが、先ずは、マントルが占める場所から
説明。
マントル・・・・地殻下部より深さ2900kmまでの領域を占める
こう言うと「地殻下部ってじゃあどこやねん、何Mなの?」という突込みが
来そうだが、地殻の厚さは場所によって著しく異なり、具体的に何Mまで
が地殻で何Mからマントルとは言いにくいのだ。でもまあ、地球の半径
4600kmからすると地殻の厚さなんて微々たる物(卵全体からすると殻
が極薄いのと同じこと)
だから、こう覚えても構わないかも
マントル・・・・ほぼ地表面より深さ2900kmまでの領域を占め、マントル
の上に極薄い地殻が載っている
では、そのマントルは一体何でできているのだろうか?実はマントルを構
成する物質は女性と女性にマメな男なら必ず知っているものなのだ。ヒン
トは「八月」である。

そうぺりドットなのだ。つまり、マントルの領域に行けば、八月生まれの女
性はおそらく天にも昇る気持ちになれるはずだろう。だって、周りには誕
生石だらけなのだから。因みに、これをちょっと科学的に言うと、マントル
はオリビン(ペリドットの学術名で鉱物)を主とするペリドタイト(カンラン岩)
から成りたっているとなる。つまり、マントルは岩石からなっているのだ。
つまり、固体!!固体と聞いて、ビックリしている人が居ると思う。「マントル
はマグマが溜まっている部分じゃないのか?」と。これが上で言った勘
違い!!もう一度言おう、マントルはマグマからできているのでなく、岩石か
らできているのだ。
マントル・・・・カンラン岩を主とする固体層
ではなんで、マントル=マグマという誤解が生じたのか?それが「対流」
である。どういう事かというと、思考プロセスとして、「流」は「流れる」⇒と
なると「液体」だ⇒「マグマ」に違いない!!。こんな感じだ。そしてそれを強
固にするものとして、小学生以来から示される地球の断面図がある。そ
こには、マントルの部分が赤く描かれている。「マントル=マグマ」説にピ
ッタリ!!こうして又一人、「マントル=マグマ」と思う人が誕生していく!!もう
マントルの部分を赤く塗るのやめませんか?
(前回の「誰でも分かる地球科学貤」で用いた断面図はしっかり、マントル
が青で塗られています。下の典型的な図との違いを堪能してください)
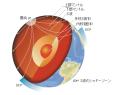
そろそろ本題に戻ろう(この勘違いネタを語りだすと熱くなって駄目だ。
でも、列記とした大学教授でも真剣にマントル=液体だという「トンデ
モ科学」を提唱している人も居るのだ!!http://www.ailab7.com/index2.htm
僕の友人にも「マントルが液体」とセミナーで並み居る教授陣を前に宣
わった奴が居た><、地球科学専攻なのに。はぁはぁ又熱くなってきた、
いい加減にこの話題から外れないと)。そのマントル、前回も言ったよう
に、3つの領域に区分される。上から、上部マントル・(遷移層)・下部マ
ントルの3つだ。このうち、遷移層を上部マントルに含むときもある。
この3つ(2つ)の区分は、前回の地殻・マントル・核の区分とは異なり、
相構造による区分である。「相」って?どこかで出てきた言葉のはず!!
そう「熱力学その後」の時に出てきた「相変化」の「相」なのだ。つまり、
化学組成はそのままでなんか見た目には違うもののように見えるあの
関係。氷⇔水⇔水蒸気のあの関係が地球の奥深くでも起きている。
具体的には、カンラン石⇔スピネル構造(リングウッドタイト)⇔ペロフ
スカイト構造という相変化が起きていて、この変化がおきるところでマ
ントルを区分している。
上部マントル・・・・カンラン石
遷移層・・・・・・・・・スピネル
下部マントル・・・・ペロフスカイト
そして、マントルの中でも特に遷移層が、地球の進化・活動を駆動し
ているマントルの進化・マントルのダイナミクスにとって、きわめて重
要な役割を果たしていると考えられ、近年多くの注目がなされている。
|